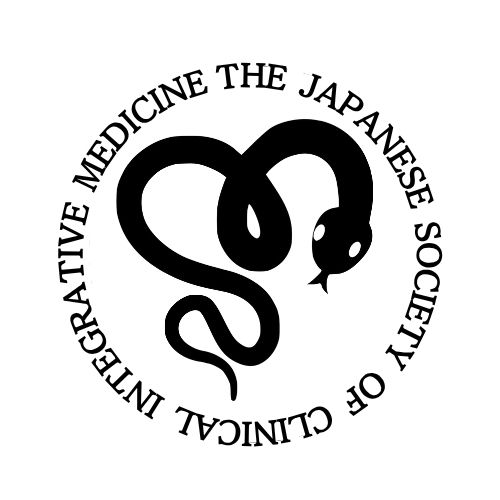自己免疫疾患(Autoimmune Disease)とは、本来は外敵(ウイルスや細菌)を攻撃するはずの免疫システムが、自分自身の正常な細胞や組織を誤って攻撃してしまう病気の総称です。発症のメカニズムは完全には解明されていませんが、遺伝的要因・環境要因(感染、ストレス、ホルモンの変化)・免疫異常などが関与していると考えられています。自己免疫疾患は多くの種類があり、攻撃される臓器や組織によって異なる症状を引き起こします。
全身性自己免疫疾患

全身エリトマトーデス(SLE)
全身性エリテマトーデス(SLE)は、免疫の異常によって自分の体を攻撃してしまう自己免疫疾患の一つです。 皮膚や関節、腎臓、神経など全身に炎症が起こり、発熱や関節の痛み、強い疲労感、顔の赤い発疹(蝶形紅斑)などの症状が現れることがあります。特に若い女性に多く、紫外線やストレス、感染症などが発症や悪化の引き金になることもあります。原因は完全には解明されていませんが、免疫の異常な働きを抑えるステロイドや免疫抑制剤などが使われることが多いです。また症状をコントロールしながら生活の質を維持することが大切で、規則正しい生活やストレス管理も重要とされています。
関節リウマチ(RA)
関節リウマチは、免疫の異常によって自分の関節を攻撃し、炎症を引き起こす自己免疫疾患です。 主に手や足の関節に腫れや痛みが現れ、進行すると関節の変形や機能障害につながることもあります。朝起きたときに関節がこわばる「朝のこわばり」が特徴的な症状の一つです。原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因やウイルス・細菌感染、ホルモンの影響などが関係していると考えられています。早期に適切な治療を行うことで関節の破壊を防ぎ、生活の質を維持することができます。リハビリや適度な運動も関節の動きを保つために重要です。
強皮症(全身性硬化症)
強皮症(全身性硬化症)は、皮膚や内臓の結合組織が異常に硬くなる自己免疫疾患です。 免疫の異常によりコラーゲンが過剰に生成されることで、皮膚が厚く硬くなるほか、血管や内臓(肺、心臓、消化管、腎臓)にも影響を及ぼすことがあります。手足の指が寒さで白くなり痛む「レイノー現象」や、皮膚の緊張による表情の変化が特徴的です。原因は不明ですが、遺伝や環境因子、免疫異常が関係していると考えられています。炎症や血管の異常を抑える薬の他に皮膚の柔軟性を保つためのリハビリや、血行を改善する生活習慣の工夫も大切です。
多発性筋炎・皮膚筋炎
多発性筋炎・皮膚筋炎は、筋肉や皮膚に炎症が起こる自己免疫疾患です。 免疫の異常により筋肉が攻撃され、徐々に筋力が低下し、手足の力が入りにくくなったり、階段の昇り降りや立ち上がりが困難になることがあります。皮膚筋炎では、これに加えて顔や手の甲、関節周りに赤紫色の発疹が現れるのが特徴です。発症の原因は不明ですが、遺伝やウイルス感染、環境因子が関係すると考えられています。早期治療が筋力の回復につながります。リハビリや適度な運動も重要で、病気の進行を抑えながら日常生活の質を維持することが大切です。
シェーグレン症候群
シェーグレン症候群は、免疫の異常により涙や唾液を分泌する腺が攻撃され、目や口が乾燥する自己免疫疾患です。 目の乾き(ドライアイ)による異物感や痛み、口の乾燥(ドライマウス)による飲み込みにくさや虫歯の増加が特徴的な症状です。関節痛や倦怠感を伴うこともあり、重症化すると肺や腎臓、神経など全身の臓器に影響を及ぼすことがあります。発症の原因は不明ですが、遺伝やウイルス感染、ホルモンの影響が関与すると考えられています。治療は症状を和らげることが中心で、人工涙液や保湿ジェルで乾燥を防ぎ、炎症を抑える薬を使用します。適切なケアを続けることで、生活の質を維持しやすくなります。
混合性結合組織病(MCTD)
混合性結合組織病(MCTD)は、全身性エリテマトーデス(SLE)、強皮症、多発性筋炎などの自己免疫疾患の特徴が混在する病気です。 免疫の異常によって、複数の結合組織(皮膚、筋肉、関節、血管、内臓)が攻撃されることで、多様な症状が現れます。手足の指が寒さで白くなる「レイノー現象」、関節の痛みや腫れ、筋力低下、皮膚の硬化、肺や心臓の障害などが主な症状です。病気の進行によって現れる症状が変化することもあり、個人差が大きいのが特徴です。原因は不明ですが、遺伝や環境因子、免疫の異常が関与していると考えられています。ステロイドや免疫抑制剤を用いて症状の進行を抑えることが一般的で、内臓への影響を防ぐことが重要です。定期的な検査や適切な治療を続けることで、病気と上手に付き合うことができます。
臓器特異性自己免疫疾患

バセドウ病
バセドウ病は、免疫の異常により甲状腺が過剰に刺激され、甲状腺ホルモンが必要以上に作られる自己免疫疾患です。 甲状腺ホルモンは新陳代謝を調節する重要なホルモンで、過剰になると体の働きが活発になりすぎ、動悸、発汗の増加、手の震え、体重減少、疲れやすさなどの症状が現れます。特徴的な症状として、目が飛び出す「眼球突出」が見られることもあります。原因は、免疫が誤って甲状腺を刺激する抗体(TSH受容体抗体)が作られることで、甲状腺が過剰にホルモンを分泌してしまうことにあります。治療には、甲状腺ホルモンの分泌を抑える抗甲状腺薬、放射線治療(アイソトープ治療)、手術などがあり、症状や患者の状態に応じて選択されます。適切な治療を行えば、症状をコントロールしながら生活することが可能です。
橋本病(慢性甲状腺炎)
橋本病(慢性甲状腺炎)は、免疫の異常により甲状腺が攻撃され、炎症を起こす自己免疫疾患です。 その結果、甲状腺の働きが低下し、甲状腺ホルモンの分泌が少なくなることで甲状腺機能低下症を引き起こします。症状としては、体のだるさ、疲れやすさ、寒がり、むくみ、体重増加、皮膚の乾燥、気分の落ち込み、動作が遅くなるなどが現れます。病気の進行が遅いため、初期には自覚症状が少なく、健康診断で甲状腺の異常を指摘されて気づくこともあります。原因は、自己免疫が甲状腺を誤って攻撃し、炎症を引き起こすことで、長期間の炎症によって甲状腺の働きが低下していきます。女性に多く、遺伝的な要因や環境因子(ストレス、ヨウ素の摂取量など)が関係していると考えられています。不足した甲状腺ホルモンを補う「甲状腺ホルモン補充療法(レボチロキシン)」を行い、ホルモンのバランスを整えることが一般的です。適切な治療を続けることで、症状をコントロールしながら日常生活を送ることができます。
1型糖尿病
1型糖尿病は、免疫の異常により膵臓のβ細胞が攻撃され、インスリンがほとんど作られなくなる自己免疫疾患です。 インスリンは血糖を下げるホルモンで、これが不足すると血糖値が異常に高くなり、体のエネルギー代謝に深刻な影響を与えます。主な症状として、異常なのどの渇き、多尿、体重減少、極度の疲れ、視力のかすみなどがあり、放置すると急激に悪化し、命に関わることもあります。発症の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因やウイルス感染が関与していると考えられています。患者は生涯にわたり適切な血糖管理を続ける必要があります。食事療法や運動療法も重要で、血糖値の急激な変動を防ぐために、バランスの取れた生活習慣が求められます。適切な治療と管理を行えば、健康的な生活を維持することが可能です。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に慢性的な炎症が起こり、びらんや潰瘍ができる自己免疫疾患の一つです。 免疫の異常により、大腸の内側が誤って攻撃されることで炎症が続き、下痢や血便、腹痛、発熱、体重減少などの症状が現れます。原因ははっきりとは分かっていませんが、遺伝的要因、腸内細菌のバランスの乱れ、ストレスや食生活などの環境因子が関係していると考えられています。症状は悪化と改善を繰り返しながら進行し、重症になると大腸全体に炎症が広がり、手術で大腸を摘出しなければならないケースもあります。治療には、炎症を抑える5-ASA製剤(メサラジン)、ステロイド、免疫抑制剤、生物学的製剤などが使われます。食事療法も重要で、腸に負担をかけない低脂肪・低刺激の食事が推奨されます。現在の医学では完治が難しいものの、適切な治療と生活管理によって症状をコントロールし、日常生活を送ることが可能です。
クローン病
クローン病は、主に小腸や大腸などの消化管に慢性的な炎症が起こる自己免疫疾患の一つです。 免疫の異常により腸の粘膜が攻撃されることで、炎症が長く続き、腹痛や下痢、発熱、体重減少、栄養吸収障害などの症状が現れます。潰瘍性大腸炎と似ていますが、クローン病は消化管のどの部分にも炎症が起こる可能性があり、腸の狭窄や瘻孔(腸の壁に穴が開く状態)などの合併症を引き起こすことがあります。原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因、腸内細菌の異常、食生活やストレスなどの環境因子が関係していると考えられています。治療には、炎症を抑える5-ASA製剤(メサラジン)、ステロイド、免疫抑制剤、生物学的製剤(抗TNF-α抗体)などが用いられます。また、腸への負担を減らすために消化の良い食事を心がけることが重要です。重症の場合、狭窄や瘻孔が悪化すると手術が必要になることもあります。現在の医学では完治が難しいものの、適切な治療と食事管理を行うことで、症状をコントロールしながら日常生活を送ることが可能です。
自己免疫性肝炎(AIH)
自己免疫性肝炎(AIH)は、免疫の異常により自分の肝臓を攻撃し、慢性的な炎症を引き起こす自己免疫疾患です。 肝細胞がダメージを受けることで、肝機能が低下し、進行すると肝硬変や肝不全につながることもあります。症状は人によって異なりますが、倦怠感、食欲不振、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、腹部の違和感、関節痛 などが見られます。病気がゆっくり進行することが多く、健康診断の血液検査で肝機能異常を指摘されて発覚するケースもあります。原因は明確には分かっていませんが、遺伝的要因やウイルス感染、ホルモンの影響などが関係していると考えられています。症状をコントロールすることができます。定期的な血液検査を行いながら、適切な治療を続けることで、肝機能を維持しながら生活することが可能です。
原発性胆汁性胆管炎(PBC)
原発性胆汁性胆管炎(PBC)は、免疫の異常によって肝臓の胆管が攻撃され、慢性的な炎症を起こす自己免疫疾患です。 胆管は胆汁を肝臓から腸へ運ぶ役割を担っていますが、炎症が続くと胆汁の流れが悪くなり(胆汁うっ滞)、肝臓にダメージが蓄積され、進行すると肝硬変へとつながることもあります。主な症状として、全身のかゆみ、倦怠感、皮膚や白目の黄ばみ(黄疸)、脂肪の消化不良による下痢や体重減少などが見られます。初期は症状がほとんどなく、健康診断の血液検査で発覚することもあります。原因ははっきりとは分かっていませんが、遺伝的要因や環境因子(感染症、ホルモンの影響など)が関係していると考えられています。症状をコントロールしながら、進行を遅らせることが治療の目的となります。早期発見と適切な治療によって、病気と付き合いながら生活することが可能です。
重症筋無力症(MG)
重症筋無力症(MG)は、免疫の異常により神経と筋肉の接合部が攻撃され、筋肉がうまく動かせなくなる自己免疫疾患です。 神経からの指令が筋肉に伝わりにくくなるため、筋力が低下し、特に体を動かすと症状が悪化しやすいのが特徴です。主な症状として、まぶたが下がる(眼瞼下垂)、物が二重に見える(複視)、話しにくい、飲み込みにくい、手足に力が入りにくい などがあり、重症化すると呼吸に関わる筋肉まで影響を受け、呼吸困難を引き起こすこともあります。原因は、免疫が誤って神経と筋肉の接合部にある「アセチルコリン受容体」を攻撃することで、神経伝達が妨げられることにあります。治療には、神経伝達を改善する薬、免疫抑制剤、生物学的製剤の他に血液浄化療法などが用いられます。適切な治療とリハビリを行うことで、日常生活を維持しながら症状をコントロールすることが可能です。
ギラン・バレー症候群
ギラン・バレー症候群は、免疫の異常により末梢神経が攻撃され、急に筋力が低下する自己免疫性の神経疾患です。 風邪や胃腸炎などの感染症の後に発症することが多く、ウイルスや細菌に対する免疫反応が誤って自分の神経を攻撃してしまうことが原因と考えられています。主な症状として、手足のしびれや筋力低下が徐々に広がり、歩きにくくなる、物を握りにくくなる などが見られます。重症化すると呼吸に関わる筋肉が麻痺し、人工呼吸器が必要になることもあります。 進行は比較的速く、発症後数日から数週間で症状が悪化するのが特徴です。免疫グロブリン療法や血液浄化療法などが知られていて、免疫の異常な働きを抑えます。回復には時間がかかることがあり、リハビリを続けながら筋力を回復させることが重要です。早期に適切な治療を受けることで、多くの患者が回復し、日常生活に戻ることができます。